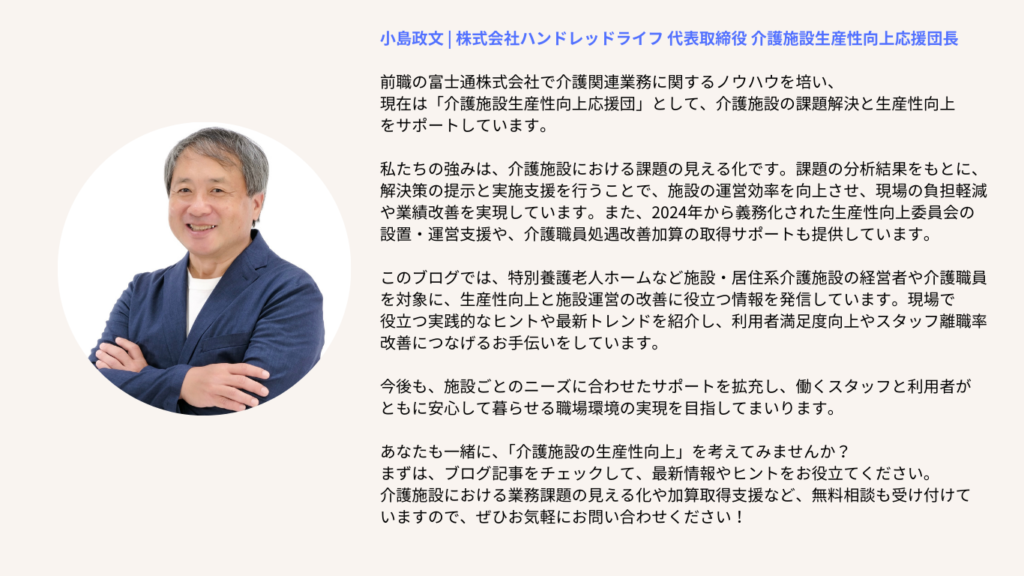介護職員の困りごと徹底解説|現場で直面する課題と改善策
介護の現場で働く職員は、日々多くの「困りごと」に直面しています。利用者対応や家族からの要望、人間関係の摩擦、さらには夜勤や身体的負担など、問題は多岐にわたります。これらを放置すれば、職員のモチベーション低下や離職につながり、施設全体の運営にも大きな影響を及ぼしかねません。本記事では「介護職員 困りごと」をテーマに、代表的な課題を整理し、その解決につながる実践的な改善策を解説します。現場で働く介護職員だけでなく、管理者や経営者にとっても有益な情報を提供し、安心して働ける職場づくりの一助となることを目指します。
目 次
1. 介護職員 困りごとの現状と背景
1-1 人材不足が生む困りごと
介護業界は慢性的な人材不足に直面しており、一人あたりの業務負担が重くなっています。結果として「時間が足りない」「十分に利用者に寄り添えない」といった介護職員の困りごとが深刻化。労働環境の厳しさが離職率を押し上げる悪循環を生んでいます。

1-2 高齢化によるケアの複雑化
利用者は複数の疾患や認知症を抱えるケースが増加し、対応の難易度が上がっています。医療知識や専門スキルが求められる場面が増え、「自分のスキルでは対応できない」という介護職員の困りごとも目立っています。
2. 介護職員 困りごとの主な内容
2-1 身体的負担と健康リスク
移乗介助や入浴介助など、身体的負荷が大きい業務は介護現場に多く、腰痛や腱鞘炎などの職業病を引き起こすことがあります。特に腰痛は、介護職員の困りごとの中でも最も多く、厚労省によると介護職の腰痛発生率は全産業平均の約3倍と報告されています。福祉用具の導入や姿勢指導研修を組み合わせることが、こうした身体的負担軽減の一手になります。
2-2 人間関係やコミュニケーションの困りごと
利用者や家族との関係に加え、同僚や上司との人間関係の摩擦も多く見られます。特に「意見が言いづらい」「相談できる環境がない」といった声が介護職員の困りごととして挙げられています。
3. 介護職員 困りごとの改善方法
3-1 ICT・DX活用による効率化
介護記録の電子化やタブレット導入は、職員の事務作業を大幅に削減します。これにより「記録に追われて利用者に向き合えない」という困りごとを解決し、ケアの質向上にもつながります。
3-2 研修と教育体制の強化
認知症ケアやコミュニケーション技術に関する定期研修やeラーニングの整備は、現場のスキル不足という困りごとを解消する手段として効果的です。特に、新人研修やメンター制度の導入は、入職初期の不安を軽減し、早期離職を防ぐ施策として注目されています。OJTだけに頼らない研修体系の標準化が、定着率の改善に直結しています。
4. 介護職員 困りごとを軽減する職場環境づくり
4-1 働き方改革と柔軟なシフト管理
夜勤や連続勤務が身体的・精神的負担を大きくする一因となっているため、シフト管理の柔軟化が求められています。短時間勤務制度や希望シフト提出の仕組みを導入することで、家庭との両立が難しいという困りごとを軽減でき、ワークライフバランスの確保にもつながります。特に、育児・介護との両立支援の文脈で注目されている取り組みです。
4-2 メンタルサポートと相談窓口の設置
職員が安心して働ける環境を整えるため、定期的な面談や外部カウンセリングを導入する施設も増えています。精神的な困りごとを早期にケアすることで、離職防止にも直結します。
5. 介護職員 困りごと改善の事例と学び
5-1 他施設の成功事例
ある施設では、ICT導入によって記録時間を30%削減し、職員が利用者と接する時間を増やすことに成功しました。これは「業務に追われて利用者に向き合えない」という困りごとを解消した好例です。
5-2 国や自治体の支援制度活用
厚労省の「介護職員処遇改善加算」や地方自治体の補助金制度を利用することで、給与・待遇面の困りごとを改善した事例もあります。制度活用は経営改善だけでなく、職員の定着促進にも大きな効果があります。
まとめ
介護職員の困りごとは「身体的負担」「人間関係」「待遇」「スキル不足」など多岐にわたります。しかし、ICT導入や研修体制の強化、柔軟な勤務制度、メンタルサポートの整備といった取り組みを組み合わせれば改善は十分可能です。また、国や自治体の制度を活用することで、職場環境をさらに良くする道も開けます。介護職員の困りごとを一つひとつ解消することは、職員自身の働きやすさだけでなく、利用者の生活の質向上にも直結します。今こそ施設全体で取り組みを強化し、安心して働ける介護現場を実現していきましょう。
介護施設の生産性向上に関するご相談は →→→ 無償相談はこちら お問い合わせよりお願いします